顎に湿疹ができる理由
顎に湿疹ができる理由は、「肌の表面的な問題」だけではありません。実は、皮膚の奥や体の内側にあるバランスの崩れが大きく関係しているのです。英気治療院では、皮膚表面のケアにとどまらず、こうした“体の内側の負担”にも着目して改善を図っています。
皮膚の下にある“内臓の圧迫”
顎の湿疹には、姿勢の乱れや内臓の位置のズレが関わっていることがあります。とくに、猫背や前傾姿勢が続くと、胃や肝臓などの内臓が圧迫され、その負担が周囲の筋肉や皮膚にも影響します。顎周りは首や顎関節と密接につながっており、内臓の影響が反映されやすい場所でもあるのです。
例えば、食後にすぐ座る、背中を丸めて長時間過ごすといった姿勢が続くと、内臓は前に押し出されて緊張状態になります。この緊張は首や顎の筋肉にも波及し、血流の滞りやリンパの流れを悪くし、結果として皮膚の再生が妨げられます。こうした背景があるため、見た目には“皮膚のトラブル”として湿疹が現れるのです。
顎は「内臓の鏡」でもある
東洋医学では、顔のパーツごとに内臓と関連付けて診る考え方があります。顎は特に「消化器系」とのつながりが深いとされています。暴飲暴食や冷たいものの摂りすぎ、食生活の乱れが続くと、胃腸の働きが弱まり、それが顎に反映されるというわけです。
つまり、顎の湿疹は「内臓からのサイン」と捉えることができるのです。「最近食べすぎていないか?」「消化の負担がかかっていないか?」と、自分の生活を振り返ってみることも、症状改善への大きな一歩となります。
顎はストレスの影響が出やすい場所
精神的な緊張やストレスも、顎の湿疹に深く関係しています。ストレスがたまると、人は無意識に歯を食いしばったり、噛みしめるクセが出やすくなります。このとき、顎の筋肉が硬くなり、血流が悪くなり、皮膚の代謝が落ちてしまいます。
また、ストレスは自律神経を乱し、ホルモンバランスの崩れにもつながります。特に皮脂の分泌が多くなることで毛穴が詰まりやすくなり、湿疹や吹き出物の原因になることも少なくありません。
顎に湿疹ができときに確認すべきこと
顎に湿疹ができると、見た目の問題だけでなく、かゆみや痛みといった不快感も伴い、日常生活に支障をきたすことがあります。この部位に現れる湿疹は、さまざまな原因が考えられるため、適切な対処を行うためにはまず原因を特定することが重要です。まずは、自然に寛解するものとそうでないものをきちんと区別して対応するために確認していく必要があります。
口囲皮膚炎の可能性
顎や口の周りに小さな赤い発疹が集中的に現れる場合、口囲皮膚炎の可能性があります。この皮膚炎は、ステロイド外用薬の長期使用や特定の化粧品、歯磨き粉などが原因で引き起こされることがあります。また、紫外線や細菌感染も悪化要因となるため、これらの使用歴や環境要因を確認することが大切です。外部からの刺激が皮膚に炎症を起こす場合があります。そんな疑いがあるときは、一時的に負担を減らす取り組みが必要になります。
ストレスの影響
過度なストレスは、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮膚のバリア機能を低下させることがあります。その結果、顎を含む顔周りに湿疹が発生しやすくなります。最近の生活環境や精神的な負担が増加していないかを振り返り、ストレス管理を行うことも重要です。
生活習慣の見直し
睡眠不足や偏った食生活も、肌の健康に影響を与えます。特にビタミンB群の不足は、皮膚トラブルを引き起こす要因となります。バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけることで、肌の回復力を高めることができます。
スキンケア製品の見直し
使用している化粧品やスキンケア製品が肌に合っていない場合、刺激となり湿疹を引き起こすことがあります。特に新しい製品を使用し始めた直後に症状が出た場合は、その製品が原因の可能性があります。低刺激性の製品を選ぶ、または一時的に使用を中止して様子を見ることをおすすめします。身につけるものや身を置く環境の影響で肌荒れが起こることもあります。まずが負担を減らすことから対処をしてみましょう。それでもなかなか改善しきらない場合は、体調に問題を抱えている場合もあります。次は、体を整えて湿疹を解消させる方法をご案内いたします。
顎の湿疹をケアするための体の整え方
顎にできる湿疹は、肌の表面的なケアだけでは根本的な改善が難しいことが多くあります。なぜなら、皮膚に現れている不調は「体の内側」や「生活習慣の乱れ」が引き金になっているからです。
ここでは、顎の湿疹を改善に導くために、体のバランスを整えるポイントをご紹介します。
姿勢を整えて「内臓の余裕」をつくる
猫背や前かがみの姿勢が続くと、胃や腸といった内臓は圧迫され、血流や神経の働きが鈍くなります。このような状態では、消化力が落ちたり、肌のターンオーバーにも悪影響を及ぼします。
正しい姿勢を意識することで、内臓に余裕ができ、代謝や排泄がスムーズになります。具体的には:
-
椅子に浅く腰かけて背筋を立てる
-
スマホを見るときは顔を下に落とさず、画面を目線の高さに上げる
-
デスクワーク中は30分に一度、軽く背伸びや肩回しをして血流を促す
など、日常の中で小さな習慣を積み重ねていくことが大切です。
呼吸を深く整える
ストレスや疲労がたまると、呼吸は自然と浅くなります。浅い呼吸は交感神経を優位にし、常に体を緊張させる状態に。これがホルモンバランスや内臓機能に影響を与え、肌にも悪影響を及ぼします。
顎の湿疹が気になる方には、「深い呼吸」で副交感神経を高め、リラックスモードを作ることがとても有効です。
1日数回でも良いので、
・鼻からゆっくり吸って
・口から長く吐く
腹式呼吸を意識する時間を取りましょう。
顎や首のコリをほぐす
顎の湿疹は、首や肩のコリとも関係しています。緊張が続くと血流やリンパの流れが悪くなり、老廃物が滞り、炎症の原因になります。
首の筋肉や顎関節の周辺を軽くマッサージしたり、肩甲骨を大きく回して柔軟性を高めることで、皮膚の再生にも良い影響があります。
日常的に意識したいのは、「食いしばり」を避けること。無意識に噛み締めていると顎周辺の筋肉が固まり、湿疹が出やすくなります。ふっと力を抜く習慣をつけましょう。
胃腸を休める食習慣
顎と関係の深い消化器官をいたわるためにも、食べすぎや夜遅くの食事は控えるようにしましょう。脂っこいもの、冷たいもの、甘いものを摂りすぎると、胃腸に負担がかかり、顎にサインが出ることがあります。
食べたものがうまく消化・吸収されるよう、よく噛んで食べる、温かい食事を選ぶといった工夫も、湿疹の改善には大切なポイントです。
最後に、間違ったケアや気を付ける習慣などをお伝えさせていただきます。
顎の湿疹でやってはいけないこと
顎に湿疹ができたとき、「とりあえず薬を塗る」「メイクで隠す」といった対処をしていませんか?
一時的に症状を抑えることはできても、根本的な改善につながらないどころか、かえって肌や体への負担を増やしてしまうことがあります。
今回は、顎の湿疹でやってはいけないことと、気をつけるべき予兆についてお伝えします。
やってはいけないこと①:むやみに薬を塗り続ける
湿疹が出ると、「まずは薬で抑えよう」と考えるのは自然なことです。しかし、ステロイドや抗菌薬を長期間・広範囲に使い続けると、皮膚が薄くなったり、逆に炎症がぶり返しやすくなったりすることがあります。
とくに顎の皮膚は繊細なため、薬による影響を受けやすい場所です。
薬を使う場合は、医師の指導のもと、使いどきを見極めることが大切です。肌が自然に治ろうとする力を妨げないよう、最小限にとどめる意識を持ちましょう。
やってはいけないこと②:肌をこすったり、洗いすぎる
湿疹が気になると、ついゴシゴシと洗いたくなるかもしれません。でも、それが皮膚バリアを壊す原因になってしまいます。
洗顔のしすぎや強い摩擦は、必要な皮脂や常在菌まで落としてしまい、肌の再生を妨げます。
・洗顔は1日2回まで
・洗顔料はよく泡立てて、手のひらで包むように優しく
・熱すぎるお湯は避け、ぬるま湯で流す
といった「守るケア」を意識しましょう。
やってはいけないこと③:メイクで隠そうとしすぎる
「赤みが気になるからファンデーションでカバーする」
これも多くの方がやってしまいがちですが、化粧品に含まれる成分が刺激となり、炎症が悪化する場合もあります。湿疹が出ているときは、肌に負担をかけないことが最優先。できる限りメイクを控えるか、低刺激のものを選ぶようにしましょう。
気をつけるべき予兆
顎の湿疹は、突然ひどくなるわけではありません。実はその前段階に、いくつかの「予兆」があります。
顎まわりの違和感やむずがゆさ
皮膚の奥で炎症が始まると、まず「かゆみ」よりも「むずむず」「チクチク」とした違和感が先に出てきます。これが湿疹の始まりのサインです。この時点で肌や体を労わる行動ができれば、悪化を防ぐことができます。
肌のキメが乱れてくる
ふと鏡を見たときに、顎の皮膚がザラついていたり、毛穴が目立ってきたりするのも、皮膚環境の変化の兆候です。これは、肌のターンオーバー(再生サイクル)が乱れているサインであり、炎症や湿疹の前触れであることが多いです。
体の疲れや睡眠の質の低下
顎の湿疹が出やすくなるとき、多くの方に共通しているのが「疲労の蓄積」や「眠りの浅さ」です。これは内臓や自律神経の働きが乱れているサインでもあります。体が無理をしているときほど、皮膚にもその負担が現れやすくなります。
まとめ
顎の湿疹を改善するには、「肌のケア」だけでなく、「体の声に気づく力」を高めることが大切です。やってはいけない習慣を見直し、ちょっとした予兆にも気づける感性を育てていきましょう。
毎日の小さな積み重ねが、トラブルのない肌へとつながっていきます。
あなたの肌と体は、きっと応えてくれるはずです。
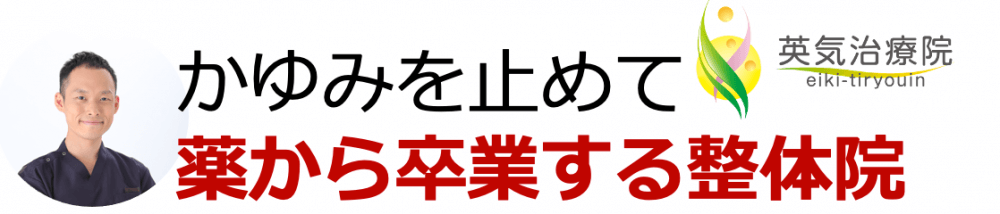
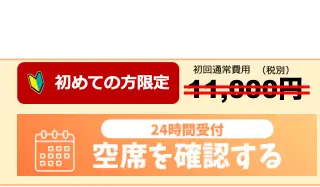







お電話ありがとうございます、
川崎市多摩区のアトピー専門整体「英気治療院」でございます。