朝起きたら、無意識のうちに頭をかいていた…。
「寝ている時に頭をかくなんて、子どもみたい」と思っていませんか?
実はこの悩み、大人にも意外と多く見られる症状です。
乾燥やフケだけが原因ではなく、体の内側に潜むストレスや血行不良、生活習慣の乱れが影響していることも少なくありません。
放っておくと、頭皮の炎症やかさぶた、抜け毛などにつながるリスクも。
「とりあえず保湿」や「シャンプーを変える」だけでは根本的な解決にならないケースが多いのです。
この記事では、寝ている間に頭をかいてしまう大人のために、本当の原因と、今日からできる具体的な対策をわかりやすく解説します。
スキンケアだけに頼らず、体の内側から整えるヒントもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
寝てる時に頭をかく大人が増えている理由
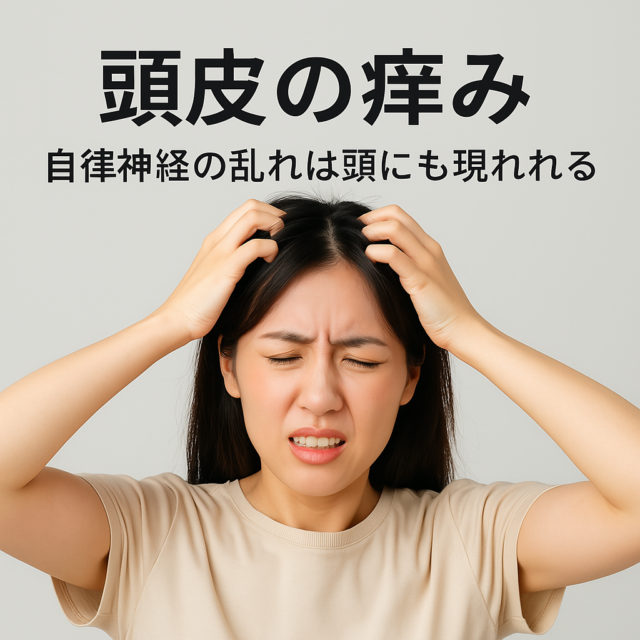
「寝ている間に無意識で頭をかいてしまう」。
子どもに多いと思われがちなこの行動ですが、実は大人にも頻繁に起こる悩みです。しかも最近では、その傾向がさらに増えていると言われています。
では、なぜ大人になってからも寝ている間に頭をかくのでしょうか?
その背景には、現代特有の生活習慣や体の状態が深く関係しています。
注目すべきは、自律神経の乱れ
日中、仕事や家事で緊張状態が続くと、夜になっても交感神経が優位なままになりやすく、睡眠中も体がリラックスしきれません。
その結果、ちょっとした皮膚の違和感を敏感に感じ取り、無意識に頭をかいてしまうのです。
さらに、慢性的なストレスや疲労の蓄積も原因のひとつです。
ストレスは皮膚のバリア機能を低下させ、乾燥や炎症を引き起こしやすくします。日中は我慢できていたかゆみが、夜になって気が緩むことで一気に表面化することもあります。
また、現代人に多いのが血流の悪化や冷え。
デスクワークやスマホ操作で首・肩がこり固まると、頭皮への血流が滞り、皮膚の代謝が落ちます。
これにより、頭皮が乾燥しやすくなり、かゆみが起こりやすい状態に。
加えて、空調による乾燥や、寝具の素材が肌に合わないといった環境的な要因も見逃せません。
冬場の暖房や夏の冷房、さらには寝汗による蒸れが、頭皮にとって負担になるケースも多いのです。
このように、寝ている間に頭をかく原因は、単なる皮膚の問題ではなく、日々の生活習慣や体の内側からくるサインであることが少なくありません。
無意識のうちに頭をかいてしまうのは、体が発する「何かおかしいよ」という警告かもしれません。
次のパートでは、こうした背景を踏まえた上で、具体的にどのような原因が隠れているのかを詳しく解説していきます。
寝てる時に頭をかく原因とは?

寝ている間に無意識で頭をかいてしまう背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
単なる「乾燥肌」だけではなく、体の内側や生活環境が影響しているケースも多く、大人特有の原因も存在します。
ここでは代表的な原因を4つの視点から詳しく見ていきましょう。
皮膚の乾燥とバリア機能の低下
まず最も多いのが、頭皮の乾燥です。
大人になると皮脂の分泌が減少しやすく、加齢や季節的な要因で頭皮が乾燥しやすくなります。
乾燥によって皮膚のバリア機能が低下すると、外部からの些細な刺激にも敏感に反応し、かゆみが起こりやすくなります。
特に冬場の暖房や、洗浄力の強いシャンプーの使い過ぎは注意が必要です。
「清潔にしよう」と思うあまり、必要な皮脂まで落としてしまい、かえってかゆみを引き起こすこともあります。
ストレスと自律神経の乱れ
現代人に多い原因が、ストレスによる自律神経の乱れです。
日中の緊張状態が続くことで交感神経が優位になり、夜になっても体がリラックスできずにいます。
この状態では、神経が過敏になり、些細な刺激でも“かゆみ信号”を出しやすくなるのです。
ストレスホルモンが増えることで、皮膚の修復力も低下し、慢性的なかゆみが続く悪循環に陥ることもあります。
血流の悪化・冷えによる影響
意外と見落とされがちなのが、血行不良や冷えです。
長時間のデスクワークやスマホ操作で首や肩がこると、頭皮への血流が悪くなり、代謝が低下します。
その結果、老廃物がたまりやすくなり、皮膚が乾燥・硬化し、かゆみが生じやすくなります。
また、冷え性の方は特に注意が必要です。
全身の巡りが悪くなることで、頭皮の環境も悪化し、夜間にかゆみを感じやすくなります。
寝具や環境による外的刺激
寝具や寝室の環境も、知らず知らずのうちにかゆみの原因になっていることがあります。
枕カバーやシーツの素材が肌に合っていなかったり、洗濯洗剤の成分が残っていたりすると、頭皮に刺激を与えてしまうことがあります。
さらに、エアコンによる乾燥や、寝汗による蒸れも頭皮への負担に。
寝ている間は無防備な状態のため、こうした外的刺激が蓄積しやすいのです。
このように、寝ている間に頭をかいてしまう原因は多岐にわたります。
次のパートでは、これらの原因を踏まえた上で、今日から実践できる具体的なセルフケアや対策方法をご紹介します。
今日からできるセルフケア・対策方法

寝ている時に頭をかいてしまうクセは、意識して直せるものではありません。
だからこそ、日中のケアや生活習慣の見直しが重要になります。
ここでは、無意識のかゆみを防ぐために、今日から始められる具体的な対策をご紹介します。
頭皮を守るシンプルなケアを意識する
まず大切なのは、過剰な洗浄を避けることです。
シャンプーは洗浄力の強いものを避け、ぬるま湯でやさしく洗うのが基本。
ゴシゴシ洗いや熱すぎるお湯は、頭皮の乾燥を悪化させ、かゆみの原因になります。
また、洗髪後は自然乾燥ではなく、ドライヤーでしっかり乾かすことも重要です。
湿ったままだと雑菌が繁殖し、頭皮環境が悪化しやすくなります。
保湿が必要な場合は、頭皮専用のローションやオイルを使い、べたつかない程度に整えましょう。
血流を促す習慣を取り入れる
頭皮のかゆみ対策には、血行改善も欠かせません。
首や肩を軽く回すストレッチや、湯船に浸かる習慣を持つことで、頭皮への血流がスムーズになります。
特に、寝る前に軽く首や肩をほぐしておくことで、睡眠中の巡りが良くなり、無意識のかゆみも起きにくくなります。
デスクワークが多い方は、1時間に1回は肩甲骨を動かすことを意識してみてください。
リラックスできる環境づくり
ストレスを和らげることも、かゆみ予防には効果的です。
深呼吸を意識したり、就寝前にスマホやPCを控えることで、自律神経が整いやすくなります。
また、寝具の見直しも忘れずに。
枕カバーやシーツは肌にやさしい素材を選び、定期的に洗濯して清潔に保ちましょう。
乾燥が気になる季節は、加湿器を使うのも効果的です。
整体や鍼灸で体のバランスを整える
セルフケアだけでは改善が難しい場合、整体や鍼灸によるアプローチも有効です。
首・肩まわりの筋肉をゆるめ、血流や自律神経のバランスを整えることで、頭皮の環境も改善しやすくなります。
特に、慢性的な肩こりや冷えを感じている方は、根本的な体質改善を視野に入れることが、かゆみの再発防止につながります。
できることから少しずつ習慣を変えていくことで、寝ている間のかゆみは確実に軽減できます。
最後に、かゆみを悪化させないために注意したいNG習慣や、日常生活での心がけについてまとめていきます。
寝てる時に頭をかく…悪化を招くNG習慣と日常の注意点
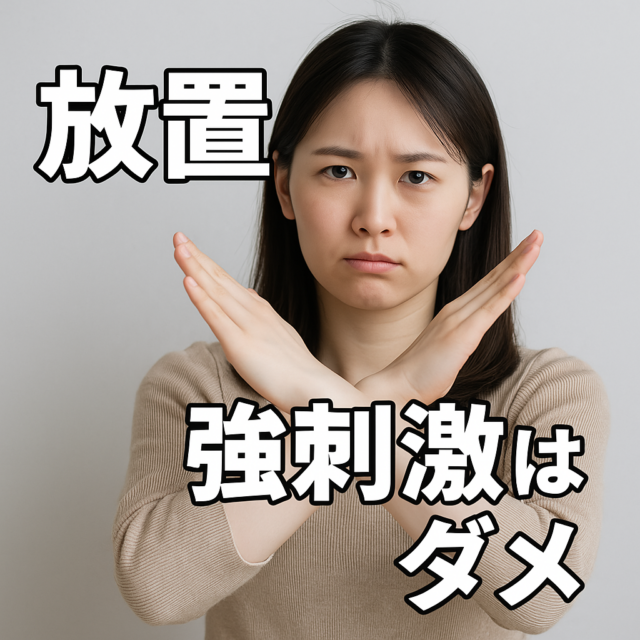
これまでお伝えしたセルフケアを実践していても、何気ない日常の習慣がかゆみを悪化させてしまうことがあります。
知らず知らずのうちに頭皮へ負担をかけていないか、ここで一度確認してみましょう。
ゴシゴシ洗い・過度なシャンプー
「しっかり洗わなきゃ」と思って、毎日ゴシゴシ洗っていませんか?
実はこの習慣が、頭皮の乾燥や炎症を引き起こす原因になっていることが多いのです。
洗いすぎは皮脂を奪い、かゆみを慢性化させる原因に。
シャンプーは適度な頻度で、やさしく洗うことが基本です。
寝る前のスマホや夜更かし
寝る直前までスマホやパソコンを使うと、脳が覚醒し、自律神経のバランスが乱れます。
これが睡眠の質を下げ、夜中にかゆみを感じやすい状態を作ってしまいます。
リラックスできる環境づくりと、質の良い睡眠を意識しましょう。
枕カバーや寝具のケアを怠る
清潔だと思っていても、枕カバーやシーツには汗や皮脂がたまりやすく、これが刺激になることもあります。
肌に直接触れるものだからこそ、こまめに洗濯し、素材も見直してみましょう。
合成繊維が刺激になる場合は、コットンやリネン素材がおすすめです。
放置することが一番のリスク
「そのうち治るだろう」と放置してしまうことが、結果的に悪化を招く最大の原因です。
無意識で掻き続けることで、頭皮が傷つき、炎症や抜け毛のリスクが高まることもあります。
早めに対策を取り、根本原因に目を向けることが大切です。
寝ている間に頭をかくという行為は、体からの小さなサインです。
日々の習慣や環境を少し見直すだけでも、かゆみを軽減し、快適な睡眠を取り戻すことができます。
無意識のかゆみに悩んでいる方は、ぜひ今回ご紹介した対策を試してみてください。
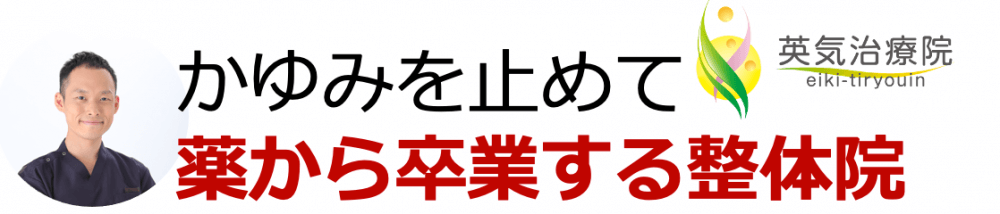
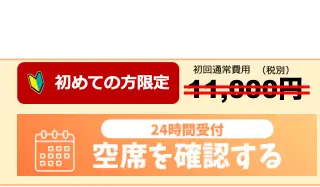







お電話ありがとうございます、
川崎市多摩区のアトピー専門整体「英気治療院」でございます。